こんにちはのり(@noriyusaku1128)です。
今回は小学5年生の夏から3年半。毎月我が家のマネー会議に参加している中学2年生の息子とお金というテーマでお話をしたいと思います。
おこづかいや欲しいものを手に入れるためには自力でなんとかしなければいけないという状況の積み重ねが、彼らが若いうちからお金の稼ぎ方、使い方を考えるようになり、社会に出て自立した生活を送る際に人生を豊かなで幸せなものにしていくと信じています。
中2息子の現在お金事情
2025年2月現在 中学2年生14歳の息子のお金回りです。
彼が保有しているおこづかいの残高は70,835円
主な財源は毎月のお手伝いの報酬であるおこづかいと親の帰省時に親せきからもらるお年玉などです。
2024年の年間収入は
毎月のお手伝い:25,060円
お年玉などのおこづかい 35,134円
合計:60,194円になっています。
年間支出は52,333円
うち2万円は自身のゲーミングPCを購入するために親に借金した返済です。
娘と違い友達と遊びに行ったり(近所の夏祭りくらい?)外食はしませんし、ほとんどがゲームソフト、PCの周辺機器、PCで作画をするためのツールである液タブの購入費などです。
この収支の差額7,861円が年間で増えた彼の資産額ということになります。
ゲーミングPCを購入した親からの借金は40,000円を返済済。残高は現時点で108,940円。
今後毎年2万円 あと6年で完済予定です。
(「息子が親から借金して将来へ投資したことについて」)
以下細かく見ていきます。
おこづかいについて
のり家では子供たちの小学生の頃からお手伝いおこづかい制です。
将来経済的自立をしたい息子ですが運用の種銭を作るには働かなければいけません。それを日常生活の中で取り入れています。
お手伝いの内容は洗濯物を干したり、ふとんを干したり、ペットの亀の水槽を洗ったりで、1回やるごとにおこづかいをもらえます。
なのでうちの場合兄妹の年齢差でもらえる金額が違うということはなく、お手伝いの回数が多いほうがたくさんおこづかいがもらえます。
その1回あたりのおこづかいですが、単価60円だったものが昨年単価100円に値上がりしました。
毎月開催しているのり家マネー会議で家計の資産額が順調に増加していることを報告したところ、
「そんなに増えているのならおこづかいの金額も上げてくれないかな?」
という息子の要望がきっかけです。
家庭の資産が増えているなら自分たちへの配分を増やしてくれてもいいんではないか、という交渉でした。
それを聞いた奥さんは「うーん」と考えて、「親の指示が出る前に必要なことを判断し、自発的にお手伝いできるのならいいよ。」と交渉成立。
実に167%のベースアップを勝ち取りました。
その後息子はコンスタントにお手伝いを続けていて毎月2,000円程度のおこづかいをもらっています。
世間的には中学生のおこづかい平均月額は2,000円~2,500円程度のようなので世間並な金額にはなっているようです。
お年玉も含めた親からのおこづかいは全額息子名義の住信SBIネット銀行の口座に入金しています。
親せきからのおこづかいも当面必要そうな現金だけを残して全額入金です。
息子は自分のスマホをつかってアプリで金額確認、振込などの管理を自分でやっています。
(「子供のスマホに入っているお金のアプリについて」)
支出の金銭感覚
次は支出です。
支出をする際も頭を使ってお金を使っています。
息子の小学生のころから「最安値.com」などの金額比較サイトや、メルカリなどを教え、同じ商品でも買う場所によって金額に差があり、比較して買ったほうがいいということは伝えてきました。
息子はそれを実践できていて、先日も欲しいゲームソフトをセールで安くなるのを待って購入しています。購入方法はPCゲーム配信プラットフォームである「STEAM」から自分のゲーミングPCにゲームソフトデータをダウンロードです。
同じタイトルがSwitchでパッケージ版で販売されているのでそれを購入しないのか?と聞いたところ
「高いんだよ。Switch版は5,000円するんだけど、STEAMで買えば素で3,990円、それが半額セールで1,995円で買えるから同じゲームが3,000円安く買える。」
という返事。事前にリサーチした上で選択していたようです。
オンライン購入の場合、まだ彼がクレジットカードを持てていないので、いったん私のクレカで決済。と同時に息子が先述した自分の銀行口座から私の口座へ同額を振込精算完了です。
一応銀行のデビットカードを作れば彼自身でオンライン決済できてしまうのですが、息子の支出を監督するという意味でこのやり方にしています。
またこれとは別の場面。先日息子の歯列矯正の検査の時にずっと口を開けていたからか、終わったあと「のどが渇いた」と訴えて来ました。対して私が「いいよ、あそこの自販機で飲み物買おう」と提案すると「いや、自販機の飲み物は高いからいいや、近くにスーパーがあったでしょ。安いからそっちにしよう。」
と答えてきました。
以上のやりとりで同じ目的を達するのであればひと手間かけても安いものを選びお金を残すという金銭感覚が息子に身についているということがわかります。
幼いころからの積み重ねが身についていく
以上中学2年生段階での息子とお金、というテーマでお話してきました。
小学生のころから
・サンタクロースのプレゼントはなくほしかったNntendo Switchは兄妹で協力してお金を貯めて中古で購入をした。
・お手伝いをしなければおこづかいはもらえない。
・紙のおこづかい帳→オンラインおこづかい帳で自分の資産を管理している。
・「最安値.com」やメルカリなど、同じものを安く買うやり方があることを教わった。
・5年生の夏から「のり家マネー会議」に参加し、給料、社会保険、税金、支出、投資、為替について毎月情報を得たり、意見を言える機会を持っている。また自身のおこづかい管理の報告をしている。
・15万円する自分のゲーミングPCを購入するときは、金利1%で親から借金をし、毎年返済しながらゲーム作成プログラミングのオンラインレッスンの受講や、自分の好きなゲームをプレイしている。
・・・等々
以上の経験を経て今の金銭感覚が育成されてきたのだと思います。
自分が得たおこづかいは自身の労働の対価であり、そのおこづかいを使って購入するからこそいかに安く購入するかということを考えることを身に着けることができたのでしょう。
以前こちらのブログでも記事にしましたが(「子どもたちの「少しの不幸」について」)、おこづかいや欲しいものを手に入れるためには自力でなんとかしなければいけないという状況の積み重ねで、彼らが若いうちからお金の稼ぎ方、使い方を考えるようになり、社会に出て自立した生活を送る際に人生を豊かなで幸せなものにしていくと信じています。
関連記事です。


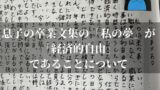
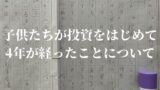
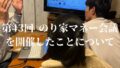

コメント